─エピローグ・ステージ2─
Fin 蒼い月を
キッチンの片づけが終わり、隼人が二階の寝室に入った時だった。
今、妻がこの寝室のバスルームで入浴をしているはずなのだが、この部屋の窓辺に人影が……。
「海人。なにをしているんだ」
「父さん」
息子は『見つかった!』とばかりに、ちょっとバツが悪そうな顔をして固まってしまった。
別に両親の寝室に出入りはするなとは言わないが……。
それでも『大人の夜のスイッチ』が既に入っていたパパとしては、妻もすっかりその気でいてくれるだろうと、彼女が入浴をしている夫妻寝室にいそいそと向かってみて、そこに息子がいるのは、『こっちも』バツが悪い思い。
しかしよく見ると、息子の手には、妻愛用の『アロマランプ』。
それは彼女が航行に出ていく前に、隔週で週末に帰ってくる娘の部屋に置いていったものだった。
そしてそれは『兄の仕事』のようにして、葉月が『お兄ちゃんお願いね』と、長男の海人に任せたお手伝い。
今は離れて暮らしている妹が帰ってくると、兄の海人は母親に言われたとおりに、妹が寝る前はアロマランプを仕掛けていた。
「これを母さんが帰ってきたら返そうと、杏奈と決めていたんだ」
「そうか。うん、喜ぶと思うよ」
「母さん、眠っている?」
息子のその一言に、隼人はどっきりとした。
栗毛の茶色い瞳、妻にそっくりな顔。妻が無邪気な顔をする時によく似ている顔。
だが、近頃周りの人々が言う。『表情が父親に似てきた』と。
それは隼人もどっきりとすることがある。海人がふと呟いた『自分なりの考え』が、自分の思っているところを言い当てられたようなことを言い出すことがあるのだ。それは決して『ママが言いそう』なことではないものだった。
そして今、息子の『眠っている?』。いつしかの、若い時の自分を思い出させる息子の母を案じる一言。
「寝ているよ。ぐっすり」
「知っているんだ。時々、朝方、こっそりと出かけている。ヴァイオリンを持って……」
「ああ、あれは──」
その先を言おうと思って、隼人は口を閉ざしてしまった。
別に息子に教えても良いのだが……。ちょっとした『パパの秘密』であるものだから、大人げなく勿体なく思ったりして。
「儀式だよ。ママの、儀式」
息子が『儀式?』と首を傾げた。
だが、父親の隼人はそれ以上は答えずに、アロマランプを準備する息子の下へと歩み寄る。
妻が趣味で集めたアロマオイルが並んでいる棚の前。そこに息子がアロマランプをセットしている。そして彼が握りしめているオイルは『ラベンダー』。杏奈が眠る時に、母親の葉月が選んでいるものだった。
「違うな。今夜はこれがいいだろう」
「オレンジ?」
コレクションの棚から、隼人は一本のオイルを勝手に選んでしまう。
まあ、なんとなくだ。妻の気分などばっちりとは言い当てられなくても、『なんとなく』。妻が遠くから帰ってきた時に良く選んでいるような気がしているだけ。
それを息子がセットしたランプのガラス小皿に張られている水の上に数滴、落とした。
「父さんは、本当に母さんのことが何でも分かるんだね」
「まあな。やっぱり夫婦だし?」
「なんだよ。毎度、のろけてくれてさ。俺、今夜は『お邪魔』だと思うから、お隣で寝るから」
「わかった。何かあったらちゃんとこっちに連絡するんだぞ」
うんと頷いてドアへと向かう息子の背を見送りながら、隼人は『なにがお邪魔だ。生意気な』と、ちょっと痛いところをつかれたようで頬が引きつっていた。
達也はまだ帰ってきていない。彼も重要なポジションに就く『陸部大佐』になっている。仕事も忙しい。それだけじゃない。仕事が終わったら、入院をしている妻のところに必ず通っている。だからここのところ帰りが遅い。だからこそ、隼人は余計に早く帰ってくるように心がけている。勿論、達也も毎日ではなく息子を不安にさせないように明るい笑顔で早めに帰ってくる日もある。それでも……。
今、息子の海人は隣の家で寝ることが多い。ひとりぼっちの晃を思ってのことだろう。
本当に兄弟。父親の面影を醸し出してきた生意気で明るい晃と、栗毛の母にそっくりに、ちょっとすうっとした澄ました顔の海人が並ぶと、そこは本当に若き日の『双子同期生』を思い起こすコンビだった。
「母さんに、おやすみって言っておいて」
「ああ。言っておく」
「……俺、母さんのこと、馬鹿にしていないよ」
「分かっている」
「俺、母さんのこと凄いと思っているよ」
「分かっているよ、海人。そして母さんも海人がそう思ってくれていることを知っているよ」
隼人が微笑むと、息子はやっと満足した顔で頬を染め、部屋を出ていった。
『見えない真実』を、不安に思い始めている息子。どこか……在りし日の『真一』を思い起こしてしまう父親だった。
そんな時、初めて。あの頃の義兄の気持ちが分かるような気もするのだ。
「いい匂い。あら? アロマランプが……」
暫くすると、葉月がバスローブを羽織ってこの部屋のシャワー室から出てきた。
「海人が杏奈の部屋から、お前のためにと……。二人で話し合っていたんだそうだ。ママが帰ってきたら返そうねと。ぐっすり眠って欲しいと……」
「えっ。そうなの!?」
驚きの後、妻の顔に広がる幸せそうな笑顔。
その笑顔を見てしまうと、隼人はとてつもなく胸が焦がれる思いがするのだ。
そんな顔をする妻に、まだ恋している。そんな顔をする妻に、まだときめいている。
そしてそんな顔をするようになった妻を見て、夫の隼人はとてつもなく幸せな気持ちになれる。
何故なら、若い頃から……いや、彼女を愛していた全てが『これ』を求めていたからだ。それが彼女を愛している夫の願いだったからだ。
今、それがここに。色々あったが、隼人はそれを自分の思うまま、そして妻に願ったままに手に入れていた。
「すごい。今日はオレンジの気分だったのよね〜。海人、知っていたのかしら?」
「違う。オイルは俺が選んだ」
たとえ息子でも、その手柄は譲らないぞと、既に男として張り合っている大人げない父親。
だってそうだろう? やっぱり栗毛のこの女性は『最後には俺のもの』なんだから。
奥さんで、ママで、お嬢さんで──そして、ウサギ。全部、俺のものだ。
隼人はそのまま、風呂上がりの妻の側に寄り、そっと抱きしめる。
妻のちょっと照れた顔に、戸惑っている顔も、若い時から変わらない。
栗毛のウサギの顔。お嬢さんの顔。こんな時、隼人は『奥さん』とは言わない。以前同様に『ウサギ』、『お嬢さん』と囁く。
潮騒がする窓が開けられているこの部屋は、あのミコノスの青い部屋で二人愛し合っていた時と変わらない。
オレンジの香りがするそよ風。
その中で妻に口づけて、柔らかな肌をそっと抱きしめて……。
静かにバスローブを脱がせて……。
風呂上がり、葉月だけのほのかな甘い匂いを嗅ぎ取ったら、もうそこには父親ではない『隼人』がいる。
狂おしい顔つきで抱きついてくる妻を、そのまま隼人も存分に抱きしめ、愛して……。
若い時の何かを奪い合うような激しい熱愛も、胸を熱くさせたものだけれど、今はもう──『ふたりで積み重ねてきた抱き方』がある。
それはいつも同じ手順かもしれない。ふとすれば『マンネリ』とも言えるかもしれない。だけれど妻の葉月は言う。『もう隼人さんしか知らないことが、いっぱいね』と。夫妻しか分からない分かち合いが、積み重ねがあった。そうでなければ『もう気持ち良くない』と妻は言う。そして隼人も分かる。妻が今、どう感じてるかも。もっと言えば、あとどれぐらいで妻の身体が震えて花開くその瞬間がやってくるのも分かる。そして妻はいつだって変わらぬ花を艶やかにほころばせ、そしてそれを熱く咲かせてくれる夫の手立てを何度でも求めてくれるのだから。
そして、今夜も──。
青い潮騒、青い夜。青い潮風に乗ってくるオレンジの香りの中。かすかな妻の甘い香りが、ふわっと鮮烈に立ち上る瞬間を、隼人の腕の中で迎えさせる。
頬を染めて力尽きていく妻を、存分に力の限りに愛してしまう男がここにいる。
「ああ、ここは私の楽園よ」
時々、独り言のように妻が呟く言葉。
「ああ……俺にも楽園だ」
力を注いでいる最中、いつも掠れた声で隼人は答える。
ふたりが見つけた『青い楽園』は、きっとこれからも。
妻が桃色に染まった頬のまま、幸せそうに眠りにつく時。
隼人はいつもそれを見て思う。
今宵も良い夢を──。
彼女と出会った時からの、その願いは変わらない。
・・・◇・◇・◇・・・
このようにお互いが留守が多かったり、すれ違いがある生活だからこそ、そのひとときはより一層に燃えることが出来るのだろうか?
あまりにも心地良いまどろみを、暖かで柔らかい妻の横で堪能していたはずだった。
少しの物音で、隼人はふと目を覚ました。
気がつけば、隣で素肌で眠っているはずの妻がいない。
しかし、すぐに見つけられた。
明かりのついてないこの寝室。
妻のクローゼットの扉。そこに水色のランジェリーを身にまとっている白い背中が見えた。
それを確かめ、隼人はまた目を閉じ……。そう、目を閉じるふりをする。『いつものこと』だ。
妻はそのまま暗がりの中、ランジェリーの上に白いカッターシャツを着込み、制服に着替える。
そして着替え終わると必ずベッドへと振り返り、『寝ているふり』をしている夫を確かめる。
あの冷めたような氷の瞳で──。
一時、そうして隼人を見つめ、葉月はヴァイオリンケースを手にして、この部屋を出て行ってしまった。
階段を降りる音。玄関のドアが静かに閉まる音。そして鍵をかける音。
やがて、玄関側のガレージから車のエンジン音。その車が走り去っていく音。そのエンジン音は、この部屋からも見えるカーブのある海際の道路へと遠のいていく。妻の赤い車が海岸沿いの道路を遠く走り去っていく姿を、隼人は窓辺から見送った。
だが、ここで隼人もじっとはしていない。
いや、している日もある。だが、今日はその気になって、隼人もすぐに制服に着替えた。
外に出るとガレージには、ファミリカーであるワゴン車が一台だけ。
隼人はそれに乗り込んだ。
妻が今、真っ赤な車で走り去っていった後を同じように走る。
先ほど寝室から見えた海岸のカーブを隼人も走る。ふと横目で見ると、今度はそこから白い我が家が見えた。
息子にも言わなかった『秘密』。
それは妻の儀式をそっと眺めること。
妻は基地へ向かったはず。
二十四時間勤務の警備口。夜明け前で辺りがほの明るくなってきた中でも、そこだけ灯りで煌々としている基地の入り口。
隼人はそこに車を停めて、出勤をしている時と同様にIDカードを差し出した。
「おはようございます、御園大佐。先ほど、ミセスも入っていきましたよ」
「うん、有難う」
若い警備員も良く知っている顔をしてくれる。
時折、夜明けにやってくるミセス准将。そしてそれを追ってくる夫の工学大佐。
彼等の微笑ましいと言いたそうな眼差しにも、隼人は照れる訳でもなく余裕に微笑み返して警備口を後にする。
車を停めたら、次は桟橋だ。しかし──隼人はここでワンテンポ置く。桟橋に着くと、既に連絡船が出た後。きっとその船には、妻の葉月が乗っていることだろう。一緒に乗る訳にはいかないのだ。
しかし暫くして帰ってきた連絡船。その船の操縦士は桟橋に着岸して、そこで空をただ見上げている隼人に気がついてくれる。
「あ、やっぱり……。出しますよ」
「いつも、すまないね」
「いいえ」
いつでも空母にいけるように、夜通し待機している連絡船の操縦士。
彼等も、警備口の隊員同様に『よく心得てくれていた』。
「いいですね。ご夫妻はいつまでも仲が良くて」
「まさか。何をしでかすか分からないから、見張っているだけさ」
「またまた。結構、密かな噂になっていますよ。妻の背を見守る夜明けのセレモニー。だけれど誰も見ることが出来ない。夜勤をすれば『見られるかも』という幻の噂なんですよ」
『このこと』で顔見知りになった操縦士の話に、今度こそ隼人は『ふうん』と素っ気ない反応。
見張っているだなんて天の邪鬼な言葉も、もう彼等には通用しないようだった。
妻は今、その『セレモニー』へと空母艦へ行ったのだ。
それはここ数年、葉月が突然に始めたこと──。
一人連絡船に乗っている間、隼人はいつも初めて追いかけた夜明けを思い返している。
数年前に『幽霊』が亡くなった知らせが入った。葉月は『そう』と、あの無感情な顔で反応しただけだった。
しかしその日、一晩越えた夜明け。隼人が眠っている間、あの寝室、今日のような夜明けに、妻が凄い追い詰められたような顔で、何通もの封筒を開け、読みふけっていたのだ。
夫が寝ている間と言うが、隼人はいつだって目が覚めている。今日のように。それだって昔から変わらぬ習慣だ。葉月だって本当は気がついているはずなのだ。自分が目を覚ますと、必ず目を覚ましている隼人のことを。
なのに葉月は『隼人さんは寝ている』としていて、そして隼人も『俺は寝ている』としている。
妻の泣く声が聞こえたあの明け方。やっと開かれた白い封書。なにが書かれていたかは、もう、隼人は聞く気はなかった。
その後だった。妻がヴァイオリンを手にして、何かに駆られるようにして基地に行き、空母に向かったのは。その時だって、隼人は気取られないようにしつつも、必死で妻の背を追った。
その夜明けに、彼女がしたのは──。
甲板で海原に向かって、夜明けの空に向かっての、ヴァイオリン演奏だった。
そしてその夜明けの甲板に出向く行動は、幾たびも繰り返された。そしてその度に隼人は思う。
眠れたのか?
どうして急にこんな儀式をするんだ?
未だに悪い夢を見るのか?
だから、何かに駆られるようにここに来てしまうのか?
心を空にぶつけるために飛びたっていた甲板。もう飛ばないから、今はただ甲板の上で、その音を飛ばすために、来てしまうのか?
お前は、まだ……空と?
幾たびか追いかけているうちに、そう思った。
でも、違う。
妻が甲板で、なにかをぶつけるように弾き始めた曲。そのエネルギーは確かに何かを振り払うものだったかもしれない。
だけれど、数曲弾き終わると、最後に彼女が必ず弾く『アヴェマリア』。
それを聴いたなら、もうなにも言えなくなるはず。
その音は、とても澄んでいて、伸びやかに、空高く昇っていく美しい音色。
心を柔らかに、そして厳かに、葉月が空に捧げる祈りは、『アヴェマリア』。
誰のためでもない。ただ、その祈りを音に乗せて、彼女の心は澄みきった小笠原の青い夜明けに溶けていくのだ。
その音を聞き届けて、隼人はそっと一人、妻を置いて先に去る。
──もう、大丈夫。彼女は穏やかに生きている。
そう思えたから、声をかけずに、隼人は去る。
そしてまたあの白い家で、妻を待つ。妻を信じて、待つ。
彼女はここでも『真っ白』になる夜明けを、自分のために。
それが葉月の『儀式』になった。
そして今宵、この夜明けも──。
隼人が連絡船を下りて、甲板に出るドアに立った時には、もう『アヴェマリア』が弾かれていた。
変わらぬその澄んだ音に、隼人はいつもほっとする。
この曲を聴いたら、今日もそっと帰ろう。そう思わせてくれる音。
そして、毎回は後を追わなくなった隼人だけれど、それでも隼人自身もこの祈るような澄んだ音を聞きたくなってしまうのだ。
葉月が今朝、そんな気分だったように。隼人も今朝は、この音を聞きたい気分だったのだ。
もう、いいだろう。
妻の祈りの儀式に満足して、隼人は空母艦の中へと向かう階段を降りようとした時だった。
……聴き覚えのある曲。
その時、薄暗い艦内にいる隼人の周りに、ふわっとした懐かしい匂いと景色が浮かび上がる。
こことは違う潮の匂い、そして石畳の街。青と白の街。
ホテルアパートの窓辺に揺れる白いカーテンの向こうから、ヴァイオリンの音。
そしてその時聴いた曲は、いつしか妻の携帯電話から流れるようになり、その着信メロディには『ハヤブサ』と登録され……。
そして結婚してからも、妻は時折、夫の隼人の前でそれを弾く。
無言で弾く。でも、妻の真剣で熱い眼差しが、隼人を見つめている。
熱い目線で届けられるその曲は、いつも隼人に捧げられる曲になっていた。
その曲を、今日に限って、妻がアヴェマリアの後に弾いている。
いや? 追いかけてきた隼人が初めて、この甲板この夜明けに聞いただけなのだろうか?
本当はいつも、隼人がいなくなった後に、弾いていたのだろうか?
「隼人さん」
その声に、隼人は驚いて……。ついに、甲板へとそのドアを出てしまっていた。
「知っていたのか……?」
気がついていたから、だから、その曲を?
そして葉月が笑った。
「ううん」
嘘だと思った。
知っているけれど、今日に限っては気がついた振りをしているのだと。
「見て、あの月」
甲板の向こうに見える白い月。
もうすぐ夜明け。
沈もうとしているその月は、夜の黄金の光を潜め、夜明けの蒼を透かすように白く儚い姿になっていた。
でも、葉月はそれを指さして笑っている。
「あの月、夜明けの月の色」
そうかもしれない。夜明けの月は儚いけれど、夜が明ける知らせをしてくれているようにも見える。
もしかして、葉月はこの月の日を選んでここに来ていたのか? 初めて知ったように思えた。
葉月はそれ以上は、何も言わなくなった。
そしてまた、あの曲を弾き始める。
隼人もふと微笑み、その妻の隣に並んだ。
「なんだ。あれを見ていたのか」
「貴方と見たくなって──」
「もっと早く一緒に見たかったな」
そう言うと、葉月が演奏しながら笑う。
何故、今日なのか分からない。
未だに何を思っているのか推し量れない彼女は今でもあるけれど。そんな彼女を隼人は今でも愛している。
「夜明けの月は、蒼い月だったんだな」
そして輝く妻の顔。
今はふたり。
この月を見て、また──。
暗闇でほのかな明かりを見つけた。
やがてその月は、大きく満ちて、夜明けを迎える。
──蒼い月。
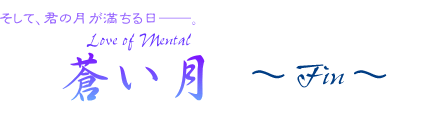
|
|||
| ■ 感想、コメントお気軽に♪ お待ちしております。返信はBLOGにて ■ |